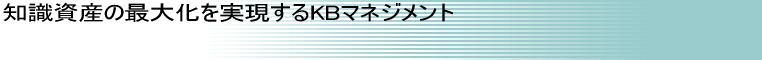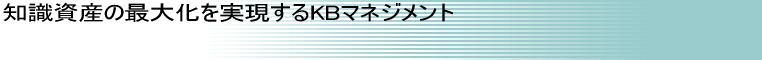|
2011年4月11日
先に進む前に、全体像を振り返ってみましょう。
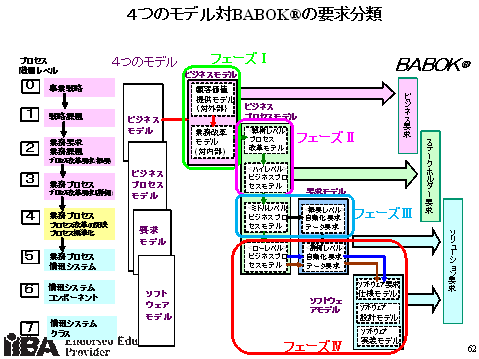
M&ERPi渡辺氏資料
先週の業務改革モデルが出来上がりましたから、上図のフェーズ1の部分に相当します。
これを基に、プロセス改革要求(概要レベル、レベル2)をまとめ、さらに、
-プロセス改革構想書
-プロジェクト計画書
をまとめます。
このフェーズの成果物はBABOKのビジネスケースに相当します。
4.機能部門の課長から課題を聴く
同様に、1レベル下の課長から課題を聴かなくてはいけません。
ここではさらに具体的な業務の課題を聴く必要がありますから、業務内容を知らなくてはいけません。質問するべき内容を知らないとどうなるでしょうか。
-製造課長へはどんなことを聴いたらよいでしょうか。製造や生産技術を熟知していないと何を聴いたらよいのかわかりませんね。またヒアリングで自由に課題を聴いていたら、発散してしまい解決しなくてもよい問題まででてくるでしょう。
-受注や調達に関することも同じです。受注のプロセス、調達のプロセスを理解していないと適切な質問すらできません。
その結果、インタビューする側に高度な属人的スキルが必要になります。スキルが不足していると、やたらと時間がかかり課題がまとまらない恐れが出てきます。
顧客の業務の詳細を理解していないとこのプロセスを分析することはできないのでしょうか。
レベル2も同じですが、ここで重要なのは「プロセス参照モデル」です。この方法論では多くのプロセス(参照モデルとして)が用意されています。レベル3では130個ほどあります。
サプライチェーンはもとより、人事系、会計系、営業、マーケティングなどのプロセスがあります。用意されていないものは、作成することが容易です。
APQC(American Productivity and Quality Center)の参照モデルを使うこともできます。
ですから、誰でも(大袈裟ですが)この参照モデルを活用することにより、インタビューが可能になります。しかもそのインタビューシートまで用意されています。
下記はレベル3プロセスのインタビュー項目の一例です。
プロセス名 質問項目 結果
[引き合いと見積り]
1.「引き合い・見積り」プロセスは存在しますか?
2.顧客からの引き合い受付はどんな方法か(Tel、書面、FAX、EDD)?
有効な顧客かどうかの選択基準は?
3.顧客の与信限度の確認方法は?
4.その顧客への販売可能な品目であることのチェック方法は?
5.品目の価格チェックや決定方法は?
支払・検収条件の決定方法は?
6.品目の納入条件(納期、納入先・場所、分納条件)の確認方法は?
7.見積り回答の承認・送付方法は?
8.顧客からの引き合いが来てから見積り回答までのリードタイムは?
一見当たり前のような項目を聴いていますが、プロセスへの入力、出力、パフォーマンスを構造化して質問していることに注目してください。これらの質問により業務プロセスとして確立されているかどうか、わかるようになっています。ビジネスルールが確立されていないと、担当者によるバラツキが生じます。リードタイムも大幅に異なります。
レベル2で改革するべきハイレベルなプロセスが明確になっていますから、そこに焦点を絞って、レベル3プロセスを分析していきます。レベル3で確立されているプロセス(全ての質問項目に明確に回答できるもの)、不備のあるプロセス(回答できない項目があるもの)が明確になってきます。不備のあるプロセスによる悪影響は何でしょうか。それらが解決するべき課題(改善するべきプロセス)として浮き上がってきます。
重要なのはこのように、トップダウンでプロセス改革を明確にし、レベルを階層的に下げていくことです。こうすることにより不必要な些細なプロセス改善を防ぐことができます。
ボトムアップでプロセスを改善しようとしても小さな改善にはなりますが、経営に影響を与えるような大きな改革につながる保証はどこにもありません。
また、このやり方で階層を下げていくと、フォーカスされているのでユーザーレベルの勝手な要望が入る余地(スコープクリープ)はありません。BABOKで重視されているトレーサビリティ(双方向)が必然的に満たされることになります。
見込生産(サプライチェーンのレベル2プロセス)のレベル3プロセスの例です。
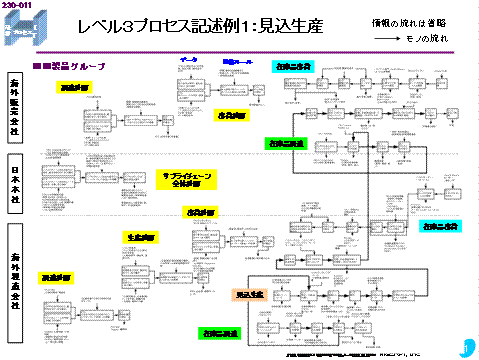
M&ERPi渡辺氏資料
スイムレーンを活用し、全世界のレベル3プロセスをA3用紙に記述します。組織のレベル3プロセス全体を把握している人は恐らく誰もいません。海外拠点のレベル3プロセスは現地の人しかわかりませんから、出かけて行って調査する必要もあります。作成するのに時間がかかりますが、完成すると課題が一目瞭然、見える化します。
あるべきプロセスが存在しない部分、プロセスはあるがビジネスルールが確立されていないプロセス。ルールはあるが守られていないプロセス。などなど。
当初課題だと思っていた部分(プロセス)とは別のプロセスに課題が見つかることもよくあります。参照モデルを活用すると短時間で真の問題の把握が可能になります。
BABOKではビジネスアナリストが真のニーズを引き出すことに責任を持つことを宣言していますが、レベル3プロセスを明確にすることが真のニーズを引き出すことにつながることが良くわかります。これはプロセス参照モデルがあるからこそできる技と言えます。
BABOKの知識エリア「引き出し」でタスクとテクニックが紹介されています。
特に「引き出しの準備をする」タスクで、質問を準備することの重要性が説かれています。また、テクニック「インタビュー」では、インタビューを組み立てることが解説されています。このビジネスアナリシス方法論では組み立てられた「インタビューシート」が用意されています。
次回は、レベル3プロセス(分析したもの)をToBeモデルへと設計していく方法です。ここで初めてITへの要求に展開されます。
特に、BABOKの「要求を割りつける」タスクの具体的方法について解説します。
  

|