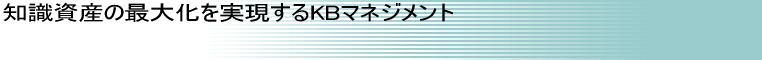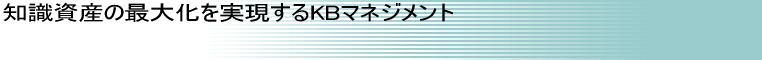2009年12月7日
去る2009年12月4日(金)に【スキル標準ユーザーズカンフェランス2010】が開催されました。
今号から3回にわたり「スキル標準成熟度モデル小委員会」の発表内容を解説します。
−「スキル標準成熟度モデル(SMM)」とは
−SMM実証実験
−実証実験(ヒアリング)の結果と今後の方向
カンフェランス資料はこちら→ カンファレンス発表資料_2009年12月4日.pdf へのリンク
1.「スキル標準成熟度モデル(SMM)」とは
SMMの目的や、経緯、メンバー、そしてSMMの概要、について解説します。
1.1 目的、経緯、メンバー
「IT人材白書2009」では、ITSSは1001名以上のIT企業の60.5%で導入されています。検討中を含めると約90%になります。でも果たして本当でしょうか。
ITSSの導入とは一体何を意味するのでしょうか。簡易診断ツール(DSやレベルチェッカー、その他)でエンジニアのレベル分布を出しただけの企業もあれば、社内認定制度を構築し役員が全員を面接し、レベルを認定している企業もあります。この両者を同じITSSを導入している、と言ってよいのでしょうか。
ITSSをベースに人材を育成しビジネス結果に活かしている企業もあれば、単に元請けからの要請により簡易診断ツールでレベルを判定しただけで人材育成とは程遠い企業もあるようです。等々...
ITSS導入の程度(レベル)には大きな温度差があると思います。
そろそろ、その温度差を測る手段が必要ではないでしょうか。
一方、前述した「IT人材白書」で多くのIT企業が導入はしたものの、ビジネス成果には至っていない企業も多いようです。導入はしたもののどうしたらビジネスに結びつけたらよいのか分からなく悩んでいます。経営者からみるとコストはかけても実利を得るには程遠い状況かもしれません。このままの状況が続くと、「ITSSは役に立たない」と感じる経営者も出てくるかもしれません。そうならないためにはどうしたら良いのでしょうか。
というわけで、ITSS導入の温度差を測る(見える化の)手段として考えたのが、この「スキル標準成熟度モデル(SMM)」です。同時にSMMは「見える化」だけでなく、改善点を一目瞭然にしてくれます。ですから具体的対策をとることができ、早くビジネス成果に結びつけることが可能になるのです。
1.1.1 目的 など
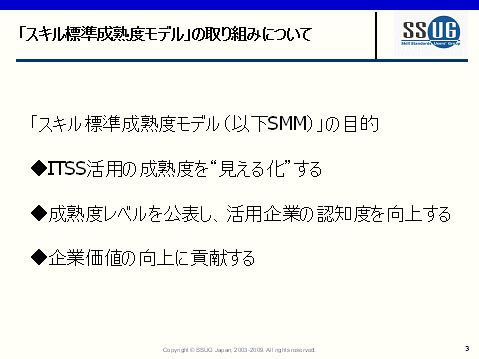
スキル標準ユーザーズカンフェランス2010発表資料より引用
SMMの大きな目的は 「見える化」です。いずれ成熟度の高い活用企業を公表したいと思います。そうすれば活用企業の認知度が向上します。そして、その活用企業の企業価値の向上に貢献することです。
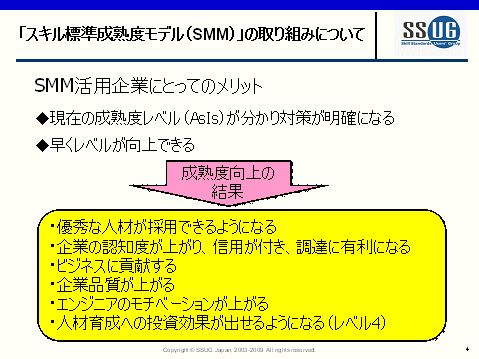
スキル標準ユーザーズカンフェランス2010発表資料より引用
成熟度(AsIs)が分かれば、改善個所が明確になりますから、具体的な対策に取り組むことができます。そして成熟度が向上すれば、図のように、「人材採用」、「外部調達」、「企業品質」などの効果が期待できます。
SMM活用企業にとって大きなメリットがあると思います。
1.1.2 経緯、メンバー
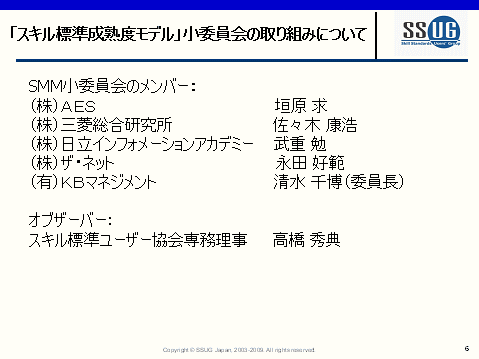
スキル標準ユーザーズカンフェランス2010発表資料より引用
2009年2月に、スキル標準ユーザー協会の認定コンサルタントコミュニティの有志が集まり、正式な小委員会としての活動を開始しました。幸い専務理事の協力も得て、オブザーバーに入ってもらいました。本格的な小委員会活動がスタートしました。
1.
2 スキル標準成熟度モデル(SMM)とは
SMMはカテゴリ、プロセス領域、ゴール、プラクティスからなります。
1.2.1 スキル標準成熟度モデルの全体像
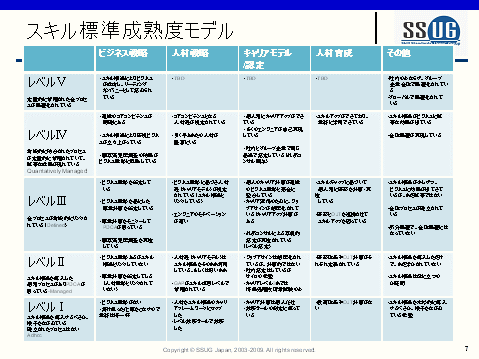
スキル標準ユーザーズカンフェランス2010発表資料より引用
スキル標準成熟度モデル(SMM)の全体像です。
4つのカテゴリーと5つのレベルからなります。
カテゴリー: ビジネス戦略、 人材戦略、 キャリアモデル/認定、 人材育成
レベル : CMMと同じ5段階
各レベルの特徴は以下のとおりです。
レベル1(Adhoc):
スキル標準を導入するか様子を眺めている状態
確立されたプロセスはありません
|
ビジネス戦略 |
人材戦略 |
キャリアモデル
/認定 |
人材育成 |
レベル
1 |
・ビジネス戦略がない
・請け負った仕事をこなすので
業務は精一杯
|
・人材をスキル標準のキャリ
アフレームワークにマップ
した
・レベル診断ツールで診断
した
|
・キャリア計画は個人任せ
・診断ツールの判定に頼って
いる
|
・教育体系やOJT計画がない
|
レベル2(Managed):
スキル標準を導入しただけ
個別プロセスがあり、その中でPDCAが回っている
その結果スキル標準導入による効果は出ていません。
レベル
2 |
・ビジネス戦略あるがスキル 標準とリンクしていない
・事業計画を策定してしる
(人材戦略とリンクされて いない)
|
・人材像(キャリアモデル)は
スキル標準をそのまま利用
している、もしくは旧いまま
・GAPがスキル項目レベル
で 管理されている
|
・ジョブアサインは制度化さ
れているが、計画的では
ない
・社内認定はしているが
サイロの状態
・キャリアレベル3までは
情報処理技術者試験のみ
|
・研修体系やOJT計画がそれぞ
れ定義されている
|
レベル3(Defined):
全プロセスが有機的にリンクしています。
スキル標準によりずつビジネスの効果が出始めます。
早くこのレベルに到達する必要があります。
レベル
3 |
・ビジネス戦略を策定して
いる
・ビジネス戦略を基にした
事業計画を策定している
・事業計画をモニターして
PDCAが回っている
・顧客満足度調査を実施
している
|
・ビジネス戦略に基づき人材 像(キャリアモデル)が規定
されている(スキル標準と
リンクしている)
・エンジニアのモチベーション
が高い
|
・個人のキャリア計画が組織
のビジネス戦略と完全に
整合している
・キャリア獲得のために、ジョ
ブアサインが制度化されて
いる(キャリアアップ計画が
ある
・外部コンサルによる客観的
認定が実施されている
(レベル認定)
|
・スキルギャップに基づいて
個人別に研修を計画・実施
している
・研修とOJTを連携させて
スキルアップを図っている
|
レベル4(Quantatively Managed):
有機的に結合したプロセスが定量的に管理されていて顕著な効果が表れている
レベル5(Optimized):
定量的に管理された全プロセスが最適化されている
1.2.2 SMMのプロセス領域
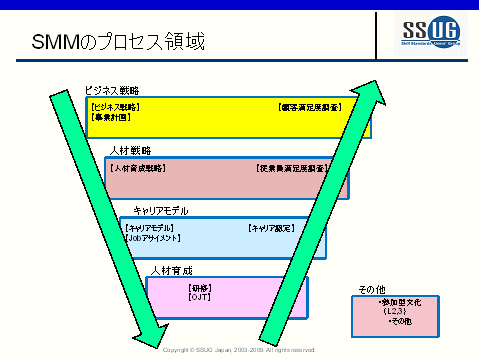
スキル標準ユーザーズカンフェランス2010発表資料より引用
各カテゴリーにはいくつかのプロセス領域があります。
カテゴリー プロセス領域
ビジネス戦略: 【ビジネス戦略】 【事業計画】 【顧客満足度調査】
人材戦略 : 【人材育成戦略】 【従業員満足度調査】
キャリアモデル/認定: 【キャリアモデル】 【Jobアサイメント】 【キャリア認定】
人材育成 : 【研修】 【OJT】
レベル3では上のように合計10個のプロセス領域があります。
そして、上図のようにV字モデルをイメージしています。
例えば、カテゴリー「キャリアモデル」では、プロセス領域【キャリアモデル】でキャリアモデルを策定し、人材ポートフォリオを提示します。それに基づいてJobアサイメントや【人材育成】プロセス領域で研修、OJTを実施します。それらの活動(プラクティス)がうまくいっているかどうかを、【キャリア認定】プロセス領域でチェックすることになります。
その上のカテゴリー「人材戦略」では、【人材育成戦略】に基づいてキャリアを定義し、スキルを定義したりします。それに基づき、「キャリアモデル/認定」「人材育成」を実施します。それらの活動がうまくいっているかを【従業員満足度調査】でチェックします。
1.2.3 プロセス領域とゴール
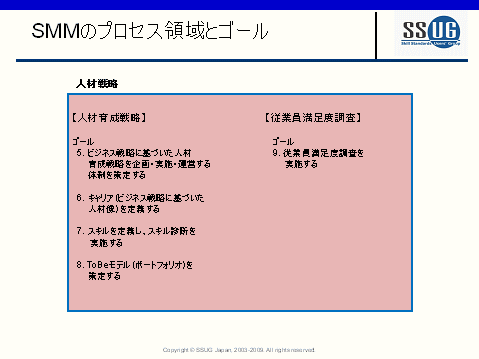
スキル標準ユーザーズカンフェランス2010発表資料より引用
プロセス領域での活動のゴールです。
【人材育成戦略】プロセス領域には、4つのゴールがあります。
−ビジネス戦略に基づいた人材育成戦略を企画・実施・運営する体制を策定する
−キャリア(ビジネス戦略に基づいた人材像)を定義する
−スキルを定義し、スキル診断を実施する
−ToBeモデル(ポートフォリオ)を策定する
【従業員満足度調査】プロセス領域は、1つのゴールです。
−従業員満足度調査を実施する
1.2.4 ゴールとプラクティス
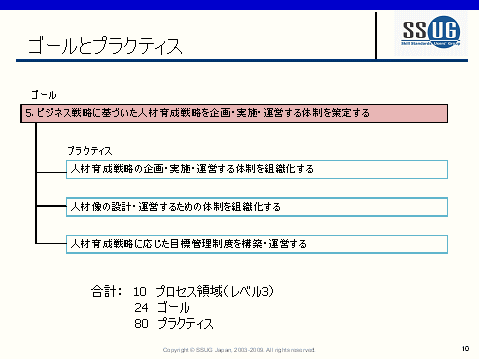
スキル標準ユーザーズカンフェランス2010発表資料より引用
各々のゴールにはそれを達成するために必要な活動としていくつかのプラクティスがあります。

|